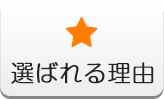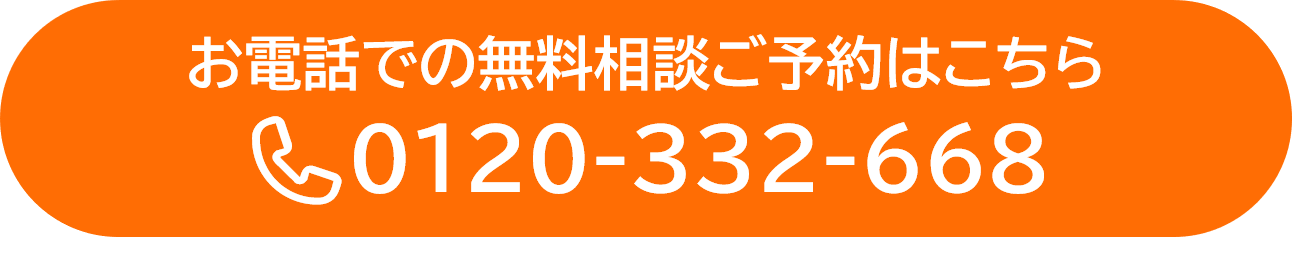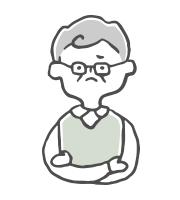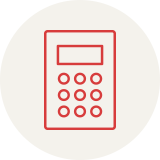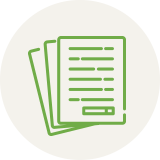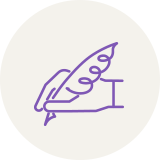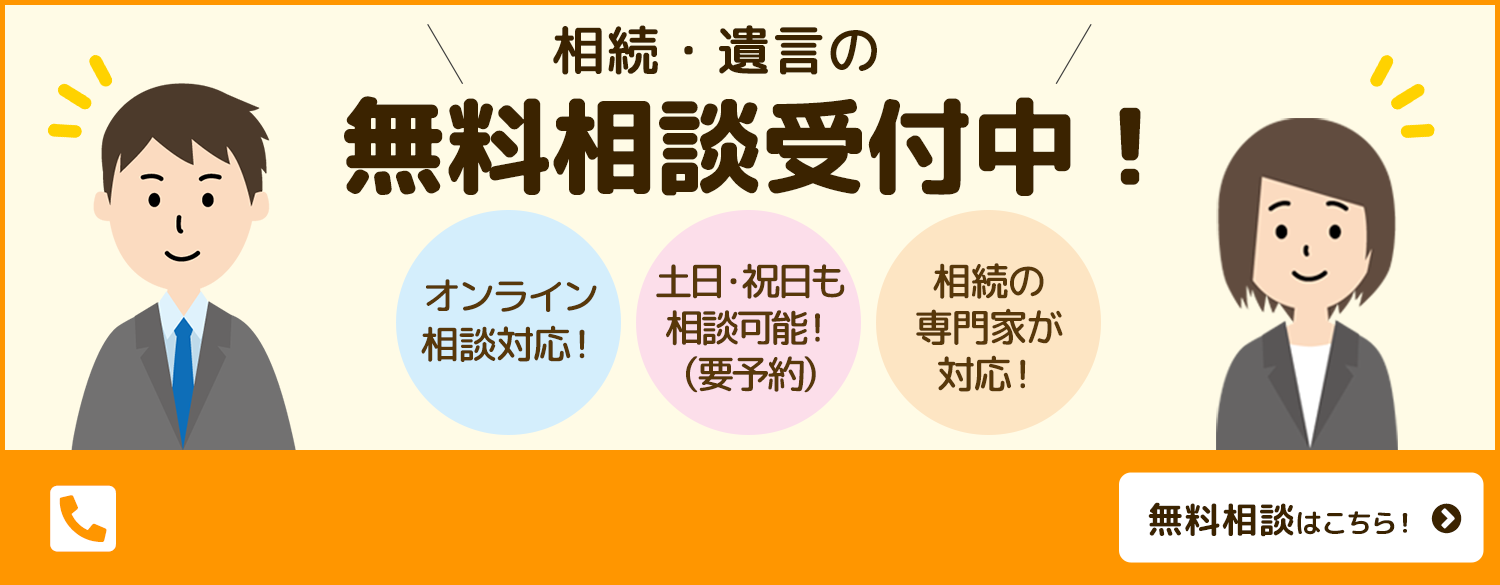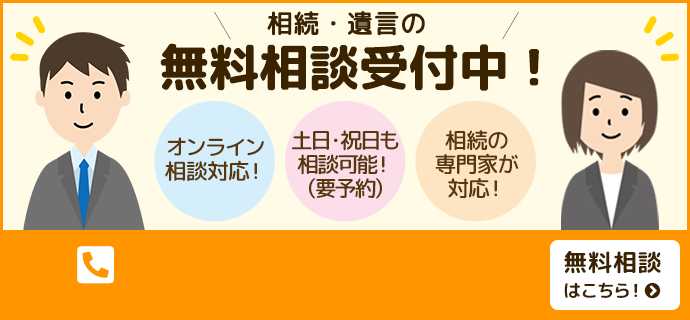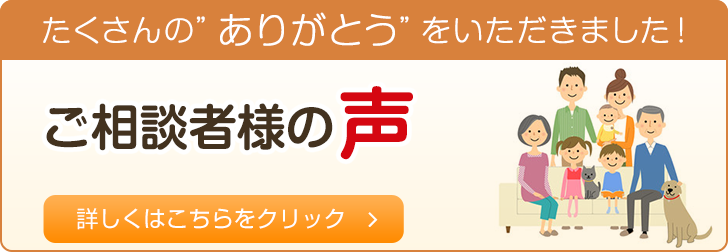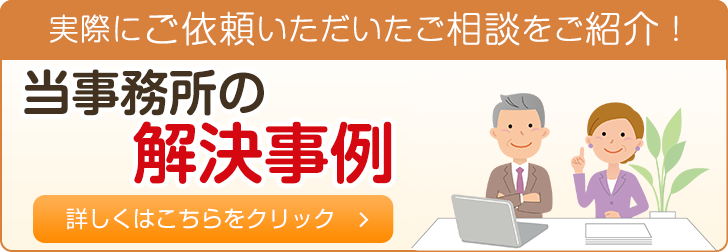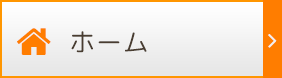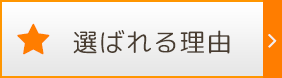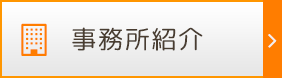【司法書士が解説】子どもがいない相続の不安を解消!配偶者を守るための最善策
「子どもがいない相続」と聞くと、「配偶者(妻または夫)が全て相続する」と考えている方が多くいらっしゃいますが、これは誤解です。
遺言書がない場合、民法で定められた法定相続人が財産を相続します。
そして、子どものいないご夫婦の場合、残された配偶者と、義理の親や兄弟姉妹が共同で相続人になるケースが多く、これが深刻なトラブルにつながることが少なくありません。
長年連れ添った配偶者に、安心して生活を送ってもらうためには、生前の対策が不可欠です。
本コラムでは、司法書士の視点から、子どもがいない 相続の基本的なルールと、配偶者を守るための最善の対策をわかりやすく解説します。
タップ/クリックで該当箇所にスクロールします。
1. 子どもがいない 相続:「誰が・どれだけ」相続する?
相続順位とは?相続人は誰になる?
法定相続人の範囲は、民法で以下のように定められています。配偶者は常に相続人となりますが、血族(配偶者以外の親族)には順位があり、先順位の人がいる場合は後順位の人は相続人になりません。
| 順位 | 相続人の範囲 |
| 常に相続人 | 配偶者 |
| 第1順位 | 子(子が亡くなっている場合は孫などの直系卑属が代襲相続) |
| 第2順位 | 直系尊属(親、親が亡くなっている場合は祖父母) |
| 第3順位 |
兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪が代襲相続) |
子どもがいない場合の法定相続分
「子どもがいない 相続」では、第1順位である子どもがいないため、相続権が第2順位または第3順位に移ります。
| 相続人 | 相続分の割合 |
| 配偶者と第2順位(親など) | 配偶者:3分の2、第2順位:3分の1 |
| 配偶者と第3順位(兄弟姉妹など) |
配偶者:4分の3、第3順位:4分の1 |
この法定相続分のルールにより、配偶者がすべての財産を相続することはできず、残りの財産は義理の親や兄弟姉妹が相続することになります。
2. 子どもがいない 相続で起こりがちなトラブル
配偶者と血族相続人が共同相続人となる場合、特に以下の点でトラブルが発生しやすくなります。
1. 遺産分割協議が難航する
残された配偶者は、義理の親族(第2・第3順位の相続人)と遺産分割の話し合い、つまり遺産分割協議をしなければなりません。
-
義理の親族との関係性:疎遠である、あるいは元々関係が良くない場合、協議がまとまりにくくなります。
-
財産への認識のずれ:義理の親族にとっては、配偶者が長年かけて築いた財産であっても、「血族の財産」として権利を主張される可能性があります。
-
相続人数の多さ: 兄弟姉妹や甥・姪が相続人になると、相続人の人数が増え、全員の合意を得ることが非常に困難になります。
2. 自宅(不動産)の分け方で揉める
遺産が自宅不動産のみ、あるいは不動産の割合が高い場合にトラブルになりやすいです。不動産は預貯金のように簡単に分割できないため、「自宅を売却して分ける」か、「配偶者が不動産を取得し、他の相続人に現金を支払う(代償金)」という選択肢になります。
特に後者の場合、配偶者が代償金を支払うだけの現金を用意できず、結果として自宅に住み続けられなくなるという深刻な事態に発展するリスクがあります。
3. 配偶者の生活を守る!司法書士が推奨する最善の対策
「子どもがいない 相続」において、残された配偶者の生活と権利を確実に守るための最も有効な対策は、遺言書を作成することです。
対策1:遺言書による財産の指定(最重要)
遺言書を作成することで、「財産全てを配偶者に相続させる」という意思を法的に実現できます。
遺言書の内容は法定相続分に優先するため、遺産分割協議をする必要がなくなり、上記のような親族間トラブルを未然に防ぐことが可能です。
対策2:兄弟姉妹には遺留分がないという大きなメリット
遺言書を作成する上で、子どもがいない相続には大きなポイントがあります。それは、法定相続人の中で兄弟姉妹(第3順位)には遺留分が認められていないという点です。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた、最低限相続できる財産の割合のことです。
-
第2順位(親・直系尊属)が相続人の場合: 親には遺留分があります。配偶者に全財産を遺す遺言を作成した場合でも、親から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。
-
第3順位(兄弟姉妹・甥姪)が相続人の場合: 兄弟姉妹には遺留分がありません。このため、「配偶者に全財産を相続させる」という遺言書を作成すれば、兄弟姉妹からの権利主張を心配する必要がなくなります。
相続人が第3順位に移る可能性が高いご夫婦は、遺言書を作成することが、配偶者を守るための最善かつ確実な対策となります。
対策3:その他の生前対策
-
生命保険の活用
-
生命保険金は原則として受取人固有の財産であり、遺産分割の対象外です。
-
受取人を配偶者に指定しておけば、他の相続人の関与なく、確実に配偶者が現金を受け取れます。
-
生前贈与
-
結婚20年以上の夫婦の場合、居住用不動産の贈与について最大2,000万円までの非課税枠(贈与税の配偶者控除)があります。
-
確実に自宅を残すための手段の一つです。
4. まとめ:専門家である司法書士にご相談ください
子どもがいない状況での相続手続きの準備は、残された配偶者の未来を守るための愛情表現です。
遺言書は、形式に不備があると無効になるリスクがあり、また、財産の内容を正確に把握した上で、トラブルを避けるための法的配慮が必要です。
さらに、遺言書執行後の不動産の相続登記は、司法書士の最も得意とする専門分野です。
当事務所は子どもがいない場合の相続でも不安を解消し、ご夫婦の想いを確実に次の世代(配偶者)へ繋ぐためのサポートをいたします。
「誰に相談すればいいかわからない」「何から始めたらいいの?」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、当司法書士事務所にご相談ください。
相続・遺言の無料相談受付中!
かなでの相続では、上尾市を中心とし、相続・遺言のご相談を初回相談無料で承っております。
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続・遺言に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の相続に詳しい司法書士・行政書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はお電話・メールにてご相談ください。
当事務所では費用を明確にし、お客様が安心してサービスをご利用できるように心掛けています。
▼メールでのお問い合わせはこちら▼(24時間受付中)